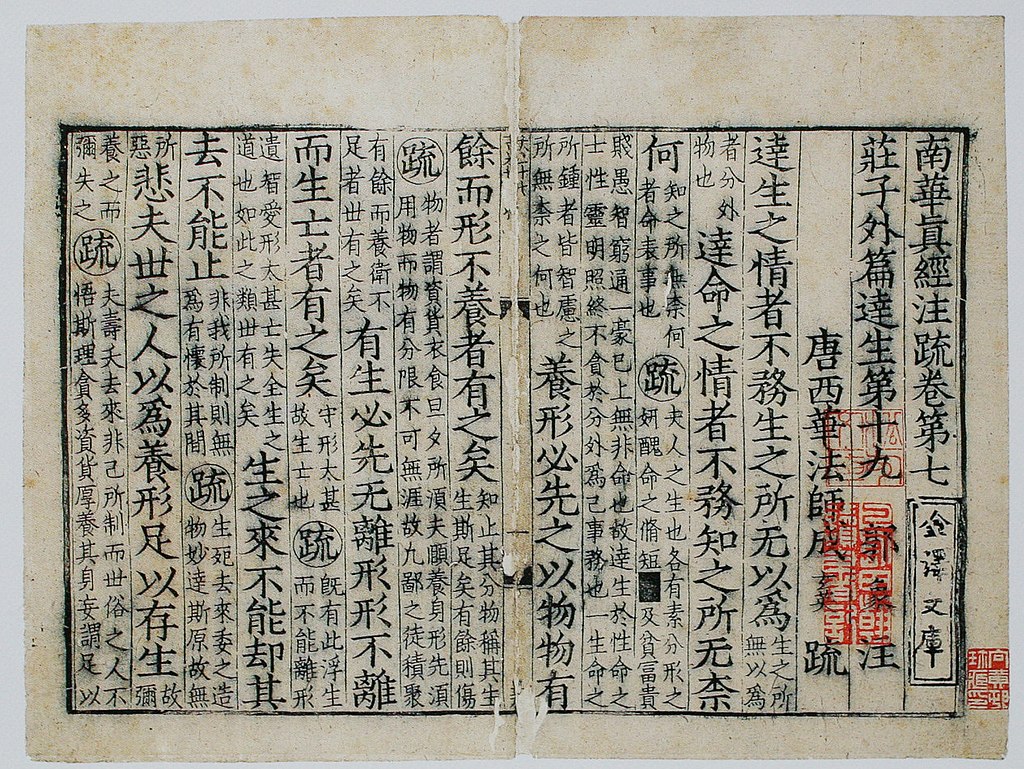【論考】シビル・ウォー アメリカ最後の日:1枚と1発


本作は2024年3月14日サウスバイ・サウスウェストというイベントにて世界初公開。それから一カ月後の4月12にアメリカとイギリスの劇場で公開。
日本で公開されたのはそれから半年が過ぎた10月4日。海外での絶賛を受け、本映画を心待ちにしていた人も多いだろう。
私も本作の日本公開を切望しており、色々と前情報を収集していた。
そのため単純な戦争映画ではなく、ジャーナリズムの視点を通して見るアメリカの内戦の物語という認識があったため、多くの人が感じる前情報と実際の作品とのズレは感じなかったのが幸いである。
結論から言えば本作は驚くべき程完成されていて、鑑賞に値する映画だ。
なぜこのような回りくどい言い回しになるかというと「すごい」であるとか「最高」という評価はあまりにも陳腐、かつこの映画のもつ本質とはズレている言葉だからだ。
この映画を小難しく例えるならば戦争映画、ではなくロードムービーであり、悪辣なヒーローズ・ジャーニーであり、自己批判を繰り返すジャーナリズムの映画だ。
本作はジャーナリズムの陳腐な独善に囚われないどころか、そこにある感情も、善悪といった二元論でさえも徹底的に取り除いたあまりにもグロテスクな本質を持っている。
だからこそ「すごい」や「最高」という評価はあまりにも本作とはズレているように感じてしまうのだ。
前述したように、本作はロードムービーであり、露悪的なヒーローズ・ジャーニーであり、自己批判を繰り返すジャーナリズムの映画である。
それぞれの項目に従ってこの映画を論考していくが、本論考には大きくネタバレを含むためそれを理解の上ご覧いただきたい。
目次
いたってシンプルなロードムービーとサブリミナル的なアメリカと戦争

本作のストーリーはいたって明確である。
キルスティン・ダンスト演じるベテラン戦場カメラマンのリーと、クルーである記者のジョエルは14カ月もの間メディアの取材に応じない大統領へ独自インタビューを行う。
最前線を飛び越えワシントンD.C.に向かう伝手としてリーの師である老記者サミーと交渉をしていた。
しかしその中でとある少女と出会う。その名はジェシー、リーに憧れる駆け出しのカメラマンだ。
これら4人からなるクルー一行は、ニューヨークを出発し、ピッツバーク、ウェストバージニア、シャーロッツビルを経由しワシントンD.C.まで旅をする。
このクルーは映画上で疑似的な家族構造となっており、リーという母の背中を見てジェシーが成長していくという王道的な物語である。

とはいえ、本質は血を超えた愛でつながる疑似家族などではなく、血でさえも感じないジャーナリズムの抱える膿を媒介しているに過ぎないのだが、
それはそれとして、成長の過程ではジョエルの支え、サミーの老婆心、そして移り行く各地の環境と出来事が影響しジェシーをジャーナリズムに落とし込ませる「ザ・ロードムービー」である。
そのため大筋は理解しやすい映画となっているだろう。
ただしこのストーリーをありきたりにしていない要素の一つがスクリーンに映し出される風景、サブリミナル的に差し込まれるアメリカが辿ってきた戦争を意識させる映像だ。
それを特に強く感じたのが冒頭給水車に群がるシーン、ウェストバージニアからシャーロッツビルにかけてのシーン、そして最終決戦となるワシントンD.C.での市街地戦のシーンだ。

本作は空撮のシーンから始まる。
このシーンではニューヨークの街並みを俯瞰していくが、その中で目に付くのは建物と建物の合間、駐車場や公園に張られているテントだ。
恐らくこれは戦火から逃れた難民たちのテントだろう。本作においてアメリカは5つの集団として分裂しており、ニューヨークはアメリカ合衆国(公式設定ではロイヤリストステイツ)に分類される。
それからシーンは給水車とそこに群がる人々、治安維持に努める警察との諍いに移る。このシーンの見方は様々あるが、難民に分け与えられる水はなくそもそもの住民、もしくは上流階級に優先的に水が配分されているのだろう。
そこにアメリカの国旗を掲げた人物が突っ込む。そして次の瞬間、集団の中で自爆テロを起こす。
このただならぬシーンを開幕お出しされて面食らわぬ人は少なくないだろうし、アメリカ人がアメリカ人に対してテロを行うという危殆に瀕する状況であるということを何よりも証明するシーンだ。
さらにこれはアメリカが関わってきた戦争を想起させるシーンの始まりでもある。
911に始まる本格的な対テロ戦、誰が何のためにこんなことをするのか一切語られないあたりアメリカ人のテロに対する衝撃の表現でもあるが、同民族間でテロを行うというアメリカが中東情勢でもたらしてきた結果を想起させるシーンと私は感じた。

次にウェストバージニアからシャーロッツビルにかけてのシーン。みんな大好き「お前はどの種類のアメリカ人だ」から燃える山、雄大な川をリトルバードが飛んでいくシーンである。
ここはベトナム戦争を示唆しているようなサブリミナルを感じた。
民間人の死体を秘密裏に処理するあの軍人は「ほの暗い作戦行動」に従事しているように感じるし、
戦火が原因か山火事が原因かはわからないが、燃え盛り火の粉が幻想的に降りかかる山の中を車の中で進むシーンはナパームを想起させる。サミーという老ジャーナリストがあの流れで息を引き取るのもなかなかに恣意的だ。
その後広がる雄大な川をリトルバードが飛び、ハンヴィーというあまり必要性を感じさせられないシーンを差し込むのも意図的に感じるし、なんならその後「地獄の黙示録」や「ワンスアンドフォーエバー」でお馴染み第1騎兵師団のヘリが出てくる。
まぁ合衆国と敵対しているのが西部連合がテキサス主体なので、師団司令部がドンピシャそこにあるからかもしれないが。
最後の舞台が野戦ではなくワシントンD.C.を舞台にした夜間の市街地戦というのも興味深い。
これも通常の軍にプラスして特殊部隊が出てきたり対テロ戦を想起させる。
このように本作はアメリカが今まで辿ってきた戦争の歴史をアメリカ国内で再現しているという見方もできる。
故に本作はかなり露悪的であるともいえ、それは風景だけではなく登場人物たちにも適用される。
露悪的なヒーローズ・ジャーニー
前述したように本作は物語論でいう「超えるべき父」としてリーが存在し「乗り越えて帰還する英雄」としてジェシーが存在するとてもシンプルな構造だ。
これをヒーローズ・ジャーニー、モノミスという。現にジェシーは打倒される大統領とその上に立つ救国の軍人を撮影したピューリッツァー賞もかくやという写真を撮影する。
まさに王道的な成長物語であり、英雄譚であるのだが多くの人がそうであるようにエンドロールで浮かぶ感情は歓喜や安堵ではなく、ビターなものだ。
そしてこの鑑賞後に残るビターさ、モヤモヤが本作の本質ともいえる。
ではこの感情を構築するに至った映画の要素は何だったのだろうか。
それはこの章と次の章で語ることになるが、まずはロードムービーの映画を語る際には避けれない風景を取り上げたい

特に印象深かったのは映画の途中で訪れる難民キャンプと前述した水を求めに群がる難民の対比だ。
この対比が一番露悪的というかグロテスクだと思うのだが、まずこの旅の途中で出てくる難民キャンプはアメリカの行政が主導ではなく国連(正確にはUNHCR)の難民キャンプなのである。
ニューヨークの難民キャンプには国連の手が入っている描写がなく、どちらかというとホームレスに近い印象を感じさせる。
だからこそ、ここで水を求めて群がる構図というのは「上流階級」と「下流階級」の争いであるともいえるし、アメリカという社会があるからこそ生まれる対立ではないだろうか。
対して国連の難民キャンプでは争いの痕跡、対立する環境というものは一切ない。年齢や世代に対する分断や、肌や血といった分断はない。
より文明的なニューヨークで難民となるよりも、より文明から逸脱し、まるでサマーキャンプのように放棄されたサッカーコートで寄り合って生活をする人々の方が分断や争いからほぼ遠い光景が描かれる。
まさにこの対比こそが露悪的でグロテスク、共感と嫌悪感の双方を抱かせる絵になっているのだ。
現代社会における分断の根源は世代間で生まれる価値観や収入ほか国からの支援で生まれる格差、肌の色で論じる人種問題、そして信仰する神とその生活基盤による宗教問題と言える。
だがそれらはすべて国家や社会という固着した価値観の中に人々が押し込まれ、限りあるリソースを余分に求めるからこそ発生している摩擦だということを本作はこれでもかと描く。
いかに文明的で進んでいるニューヨークであってもアメリカという枠組み、生活に必要な衣食住を自身で確保する資本主義社会だからこそ「差」が生まれるのである。
対して難民キャンプでは衣食住が国連という上位存在によって等しく管理分配される。人々が意思を持ち富もうとするよりも、まるで口にパイプを突っ込まれたガチョウのごとく何をせずとも衣食住が保証されれば人々は「差」という価値すら持たない。

このように本質はヒーローズ・ジャーニーであるものの、劇中で描き出されるのはアメリカの歪曲な問題とそれに対する過激ともいえるアンサーの繰り返しだ。
同じアメリカ人でありながらも分からない敵と殺し合うこと、またそれから発展した内戦への不干渉、ハイスクールで同じだった学友へのリンチ。
様々なシーンで描かれるこれらは、アメリカが内包する問題に対するアンサーとして徹底的に「思考(興味)の放棄」が共通している。
これが物語のビターさ=問題に直面させられるもそれに対して答えを放棄し続けて前へ進むという「露悪的なヒーローズ・ジャーニー」になっているのだ。
自己批判を繰り返すジャーナリズム「Take a shot」は誰を殺すのか
実は本作を鑑賞した直後は少し違ったイメージを持っていた。
それはジャーナリズムを軸とした映画でありつつも、それに対する自己批判性がないことに少し傲慢さを感じていたのだ。
フェイクニュースが跋扈する現代において、メディアというものは事実だけではなく虚構さえも事実としてしまう危険性を孕んでいる。
そもそも我々は過去にもジャーナリズムに対する問題提起を行ってきた歴史がある。報道か人命か、それを代表するのがまさに「ハゲワシと少女」だろう。
このようなジャーナリズムに対する自己批判性が本作には欠落している………と思っていたが、鑑賞後に時間が経つごとに本作にもしっかりとした自己批判性があると感じた。
本作の自己批判性はどこにあるのか、それは冒頭リーとジェシーが会話する「私が倒れたら写真を撮るのか」という会話、そして「Take a Shot」というダブルミーニング、ホワイトハウス襲撃時にシャッターを切るジェシーの表情に集約されている。

「Take a shot」日本語字幕では墜落したヘリを撮影するようにジェシーへ促すリーの発言だ。
お分かりの通りこの言葉には複数の意味がある。劇中のように写真を取る意味もあれば、やってみる(機会を逃がさない)という意味も、銃を撃つという意味もある。
写真を撮るように促すだけならば「take a photo」や「take a picture」など他の言い回しも多くあるのにもかかわらず「Take a shot」にこだわった理由はなんだろうか。
銃を撃つ、いわゆる銃のトリガーを引く行為だが、これは結果として他者を殺す行為である。この行為は本作において多く描かれてきた。
それこそ前項で軽く記載したように様々な理由でトリガーを引く(引いたであろう)シーンが出てくる
・あまり話さなかったが高校の同級生が盗みに入ったのでリンチをした上吊るしているガソリンスタンドのシーン
・命乞いをする兵士を民兵が撃ち殺すシーン
・正体の分からないスナイパーを仕留めるシーン
・アメリカ人じゃないと分かるや否や撃ち殺す赤サングラス軍人
などなど。
どんな言い分があるにせよ、そもそもアメリカに住んでいる人をアメリカ人として定義するのであれば、単純な殺人ではない同族殺しを戦争だからという理由で行えるのはなぜか。
なぜ人々は「Take a shot」出来るのか。私は自身の心を殺すからこそ「Take a shot」出来るのではないかと考えている。
戦争で人を撃ち殺すことが国益のためとはいえ、帰還後にPTSDを発症することも多い中、そのような描写が劇中になく、またそれを将来的に想起させるような描写もない。
それはこの物語に出てくるほぼ全ての人が徹底的に敵という他人に無関心であること、敵ではなく自身の心を殺して「私たち」と「他者」を分断させているからだと感じた。

同様のことがリーとジェシーにも言える。
紛争の中でひたすらにシャッターを切る。誰かが倒れても「Take a Shot」し続ける。それは彼女たちが彼女自身の心を殺し続ける行為の上で成立している。
ホワイトハウスでの銃撃シーン。リーはジェシーをかばい銃弾に倒れる。しかしジェシーはリーが倒れる様子を何枚にもわたって撮影する。
ジェシーのカメラはレトロなフィルムカメラだ。写真を取るたびにレバーを倒し、フィルムを巻いてシャッターを押す。
一枚ごとにレバーを倒すそのしぐさは、まるで銃のコッキングのようである。
そしてジェシーは大統領の写真を撮るとき、まるでそこに彼女の心が無いような表情でシャッターを押すのだ。
写真を撮る行為、銃で人を撃ち殺す行為、そのどちらもが本作では「自身の心を殺す行為」として描かれている。
だからこそ本作はジャーナリズムの自己批判性が含まれている。
写真は論争を生むが、論争は写真を生み出すのだろうか?

答えはノーだ。論争は写真というジャーナリズムを生み出すことに直接的な関係はない。
このようにジャーナリズムとは「自身の心を殺す行為」であって、そのアウトプットが写真である。そして論争とはそのアウトプットに対して対外的に生まれるものだ。
撮影者の意図しない方向に論争が生まれることもある。というのはジャーナリズムにおいても芸術においても同じ問題を抱えているが、写真や作品に主張はあれど思想がないように、主張に思想を結びつけるのは往々にして鑑賞側なのだ。
そしてそれを踏まえたうえで、直近のアンチジャーナリズム的な思想に対する批判、マスメディア軽視に対する批判。
ジャーナリズムとは本来どうあるべきなのか、そこに人間性はあるのかという自己批判性、徹底的に向き合う姿勢が1つのテーマとして本作に組み込まれている。
蛇足かもしれないが、上記の論考を補足する内容が2つあるので書いておく。

1つはみんな大好き赤サングラス軍人。人種差別的かつ話の通じない彼の姿に恐怖を覚える人は多かったようだが、突き詰めれば彼の行動原理は「彼なり」のアメリカらしさの押し付けであるといえる。
アメリカは多民族国家である以前に、先住民を放逐して成立した移民国家の最たる例でもある。それから歴史を得ることでアメリカはアメリカのアイデンティティを獲得したと感じてしまうが、
アメリカらしさというのはかなり個人的な価値観、人によって変わるものだと思い知らされた。
彼が言うにはコロラドやミズーリがアメリカらしく、ロイターという響きはアメリカらしくない(実際ロイターはドイツ系ユダヤ人が創業者)
ジョエルに対しても懐疑的だったのは彼が南米系であったからだし、同僚に関しては中国出身だと分かるや否や殺された。
白人で、アメリカの州で生まれることが彼なりのアメリカらしさなのだろう。
前述したように本当のアメリカ人とは先住民であり、彼なりのアメリカらしさが元をたどればイギリス人なのだが、彼の人となりを見るに歴史的正確性は思想を矯正させることは出来ないということである。
これもとどのつまり「自身のルーツや心を殺して」「彼の都合のいいように解釈する」ということである。

2つめはリーの変化だ。
師であるサミーが殺されても動揺しなかったリーだが、ワシントンD.C.の決戦では半狂乱になりホワイトハウスに入るまでシャッターを切るシーンがない。
戦場で死ぬ人を見続けるよりも、自身の縁ある人を失うことで彼女は彼女自身の心を殺すことが出来なくなったということではないだろうか。
旅立ってすぐのガソリンスタンドのシーンでは、民兵がドン引きするような発言(写真を撮ってあげるから吊るされた人の前でポーズして)まで言ってのける彼女が形無しになるということは、表に出さない。もしくは写真一筋で生きてきた彼女なりの表現・昇華方法がなかったとも言えるが、心を殺すという行為が出来なくなった。サミーの遺体の写真を消すあのカットも、ジャーナリズムが根底にある戦場カメラマンとしての終わりを予期した描写ともいえる。
もしくは一定ヒーローズ・ジャーニーとしての物語構造、父を超える子としての表現を前面に出すための描写だったかもしれないが。
なぜこの映画はこんなにグロテスクなのか
本作はアメリカンドリームや自由の国、強い国家というようなアメリカ神話を徹底的に破壊するグロテスクな映画ともいえる。
現実味がある、共感性があるからこそ「確かにそうなるよな」という劇に対する真実味を想起させるし「とはいえあまりにも悲惨だ」という嫌悪感も同時に持たせる。
このような感想を持つのは本作がアメリカ人から見たアメリカの映画ではないからかもしれない

本作の監督であるアレックス・ガーランドは「28日後…」の脚本や「エクス・マキナ」の監督を経験しているが、その前は戦場カメラマンを目指していたという。
だからある意味本作は彼なりの経験や価値観が色濃く反映された作品であるともいえるのだが、実はこの監督、出生地はイギリスのロンドンである。
つまり本作のアメリカはアメリカ人がその目で見た危機的なアメリカ、ではなく外から見たアメリカという国の神話が崩壊していく様子であるともいえる。
そしてこのような政府の堕落によるアメリカンスピリッツ、アメリカ神話の崩壊というのは実はイギリスの十八番ともいえる。
かなり前に私がnoteに投稿したRedDeadRedemptionシリーズの論考がある。これでも言及しているが、実はこのシリーズの開発であるRockstarGamesの源流はイギリスである(まぁスタジオでいうとロックスター・サンディエゴだが)
このゲームも失われていくアメリカの荒野とそこに存在するフロンティアスピリットという幻想が、政府や工業化の波によって崩壊していくという背景があるからこそ奥深さを感じる作品になっている。
まぁこのシリーズが持つリアリティというのは、どちらかというとシビルウォーのような映像の身近さというよりは食事や馬の世話といった細かい動作をプレイヤーに任せるというインタラクティブなシステムを用いて感じさせるものだが。
閑話休題
とにもかくにも、このような作品が立て続けにイギリスを源流とするクリエイターから出るというのは興味深い。彼らの文化がそうさせるのか、彼らの教育がそうさせるのかはわからない。
ただ舞台となったアメリカでは「なんでこんないい作品がアメリカから出ないんだ」という発言もあるようだが、ほぼ我が国が「日本を舞台にしたゲームが日本のスタジオから出ないなんて嘆かわしい」と言っているのと同じものだなと感じる。
私としては出るほうが難しいと思っている、自分の国のことを一番知っているのが自分たちだ、という価値は傲慢である。それこそ本作の赤サングラス軍人と同じ価値観と言える。
私たちが「Take a shot」してしまわないように、対外的に俯瞰し俯瞰される視点を認め無関心にならないことが大事であると思うのだ。